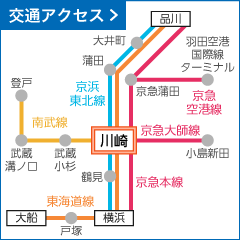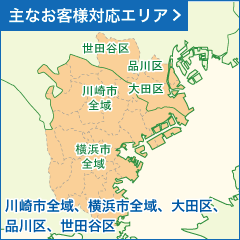不動産を相続放棄するには
地方を中心に、相続した土地を処分できず、管理費用ばかりかかって困っているというご相談を多く受けます。
こうしたいわゆる「負」動産の相続を防ぐための法的手続が相続放棄の手続ですが、この相続放棄の手続には留意事項や思わぬ法的制約、デメリットもあるため注意が必要です。以下では不動産を中心とした相続放棄の手続について解説します。
相続放棄の期間制限とは
相続放棄には相続開始を知った時から3カ月以内という期間制限があります。これを熟慮期間といいますが、そもそも相続人が被相続人に債務があったことを認識できないと相続放棄の手続を取る動機も生じようがないということなどの事情もあり、この熟慮期間については実務上比較的緩やかに解されているところもあります。もちろん、油断は禁物です。
相続放棄の対象とは
相続放棄は、被相続人の債務だけでなく、保有資産、債権などのあらゆる所有財産を放棄しなければなりません。一部を放棄し、その他は放棄しないという判断は許されないのです。被相続人の債権者の立場を考えますと、当然の帰結ですね。
相続放棄の判断が難しくなるケースとは
相続財産に多種多様な不動産が含まれている場合、相続放棄の判断が難しくなります。
不動産の中には都市部の一戸建てやマンション、テナントビル、駐車場といった資産性の高いものがある一方で、地方の実家、空き家、農地、空き地、山林など資産性が問題となる(一般的には、乏しい)ものも少なくありません。
不動産の相続に伴う負担、リスクとは
不動産を相続して所有すると、固定資産税・都市計画税や建物の維持修繕費用、山林の伐採費用といった負担が発生します。老朽化した実家やアパートは、相続後すぐに修繕費用が発生することが少なくありません。こうした費用負担を怠ると入居者や近隣住民を巻き込んだ事故の発生などにもつながり、相続人の方が被害者に対する損害賠償責任を負うことにもつながりかねません。
また、地方の山林、農地、空き地や空き家などは相続してみても買い手がつかないというリスクを抱えることが少なくありません。
不動産を相続するに当たって検討すべきポイントとは
以上のような事情を踏まえた上で、不動産を相続するかどうか検討する際のポイントとしては、以下のような項目を挙げたいと思います。
- 固定資産税・都市計画税や維持修繕費用、伐採費用などの費用を負担することができるか
- 居住するか賃貸に出すことで有効活用できるか、
- 売却を検討する場合、利益を出せる見込みはあるか、そもそも売却できる見込みがあるか
補足・相続人全員が相続放棄した場合の管理責任
なお、相続人全員が不動産を相続放棄した場合、相続放棄すれば当該不動産の管理責任を逃れるわけではなく、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任するまでは一定の管理責任が相続人全員に発生しますので、注意が必要です。
相続財産管理人が選任されるまでは相続人全員による相続放棄後1~2カ月程度ですが、その間相続放棄された不動産が全く管理されないことでその近隣住民に迷惑が及ぶことを防止する趣旨です。
相続や遺言の問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非お気軽に弊事務所までご相談いただくことをおすすめ致します。